業務の効率化や生産性向上を目的に、生成AIの導入を検討する企業が増えています。
一方で、「社内にAIの知見がない」「セキュリティや法務の承認が不安」「どこから着手すればよいかわからない」といった声も多く聞かれます。
こうした課題を解決する手段として注目されているのが、生成AI導入支援サービスです。
本記事では、導入支援の流れやメリット、失敗しない選び方に加え、実績あるサービス16社を比較しながら詳しくご紹介します。
自社に最適な導入方法を見つけたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
生成AI導入支援サービスおすすめ16選を徹底比較
生成AIの導入が加速する中で、「ツールはあっても、業務にどう落とし込めばよいかわからない」という課題を抱える企業は少なくありません。
生成AI導入支援サービスは、単なる技術導入にとどまらず、活用設計・社内展開・セキュリティ整備・人材教育までを一貫して支援してくれる点が特長です。
本章では、そうしたニーズに応える実績豊富な16社をピックアップし、対応範囲・得意業界・導入支援の進め方・社内稟議対策の観点から比較します。
- AI-Starter|クラスメソッド株式会社
- AI Going 環境構築|株式会社ブルートーン
- 生成AI環境構築支援サービス|株式会社BeeX
- Enterprise向け 生成AI導入支援サービス|株式会社セゾンテクノロジー
- 生成AI活用支援|株式会社ベルテクス・パートナーズ
- 生成AI導入支援サービス|TIS株式会社
- 生成AI導入支援チーム|GMOコネクト株式会社
- 生成AIセキュリティリスクマネジメント支援|株式会社GRCS
- GMO即レスAI|GMOペパボ株式会社
- cloudpack 生成AI導入・活用支援サービス|アイレット株式会社
- 生成AIコンサルティング|NOVEL株式会社
- 生成AI導入支援サービス|株式会社キカガク
- Graffer AI Solution 伴走支援|株式会社グラファー
- 生成AI活用支援|株式会社メンバーズ
- 生成AIコンサルティング|ナイル株式会社
- AI導入支援サービス|株式会社FRONTEO
各社の特徴を理解することで、自社に合ったパートナーを選ぶための判断材料が得られるはずです。
AI-Starter|クラスメソッド株式会社
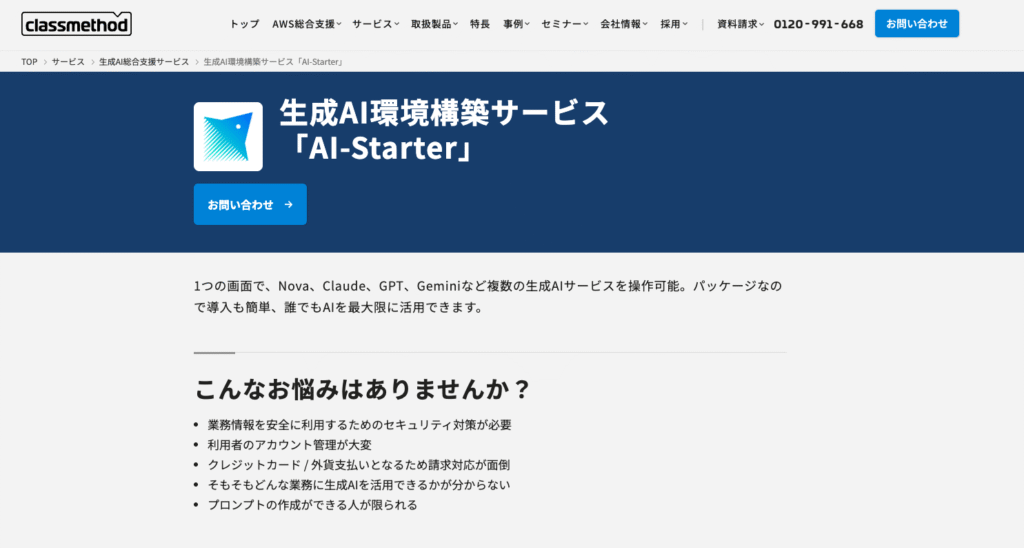
AI-Starterは、AWSのパートナーとして実績豊富なクラスメソッド株式会社が提供する生成AI導入支援サービスです。
サービスは社内での活用シーンの整理から、セキュリティ・ガバナンス要件を満たすシステム設計、プロトタイプ開発までを一気通貫でサポートしてくれます。
特に、生成AI活用における個人情報や業務データの安全管理を重視しており、法務・情報セキュリティ部門との連携も意識された構成が強みです。
また、サポート内容はテンプレート的な導入にとどまらず、利用部門ごとの課題やワークフローに合わせた設計が可能で、「どこから始めればよいかわからない」という企業にも向いています。
業種横断的に豊富な支援実績があり、内部PoCで成果を見ながら導入判断ができるため、慎重な社内稟議プロセスにも対応しやすい点が評価されています。
AI Going 環境構築|株式会社ブルートーン

AI Goingは株式会社ブルートーンが提供する生成AI導入支援サービスで、特に「自社内でのAI運用環境構築」に強みがあります。
大規模言語モデル(LLM)やCrew・Dify・Azure OpenAI Serviceなどの生成AI基盤を活用しながら、自社環境(主にクラウド)に合わせた設計が可能です。
そのため、自社データを守りながら生成AIを活用したい企業に適しています。
AI活用の導線やセキュリティ設計を含むPoC(概念実証)からのサポートに対応しており、導入初期からのステップが明確なのも特徴です。
特に「できるだけ自社の手で開発・運用したいが、最初の設計や基盤整備に不安がある」といったニーズに応えるサービス内容で、技術内製を目指す企業の伴走型パートナーとして選ばれています。
生成AI環境構築支援サービス|株式会社BeeX
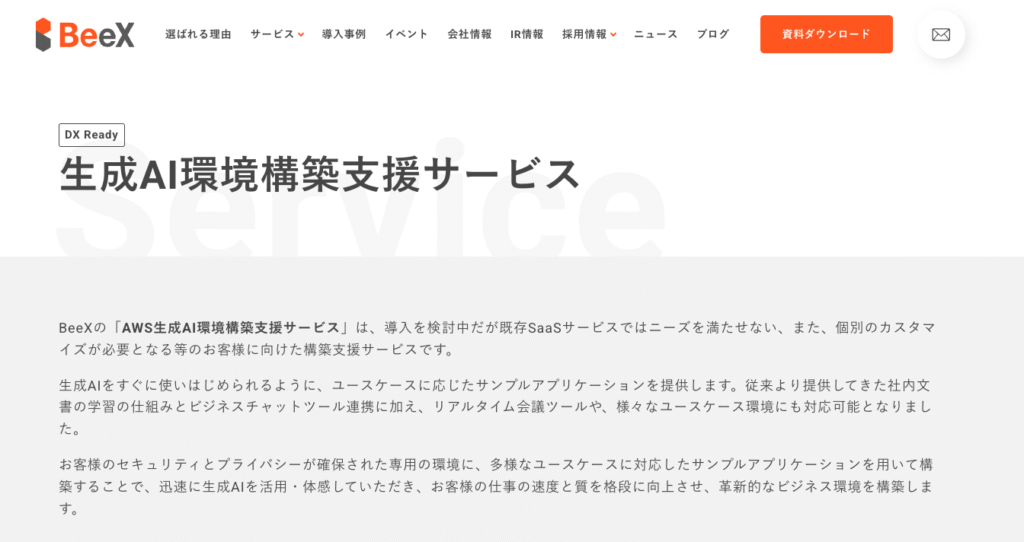
株式会社BeeXが提供する「生成AI環境構築支援サービス」は、クラウドインフラの構築・運用に強みをもつ同社ならではの支援体制が特徴です。
特に、SAPなどの基幹システムと生成AIを連携させる環境構築に実績があり、エンタープライズ領域での利用を想定したサポートに適しています。
セキュリティ要件が厳しい企業向けに、アクセス権限の分離やデータ暗号化設計など、クラウド基盤における安全性と拡張性を両立する構成が可能です。
また、AWSやGoogle Cloudといった複数のクラウドに対応しており、将来的なスケーラビリティも視野に入れた設計が行えるのもポイントです。
情報システム部門と法務・監査部門の両方を納得させられる技術支援を求める企業に向いています。
Enterprise向け 生成AI導入支援サービス|株式会社セゾンテクノロジー
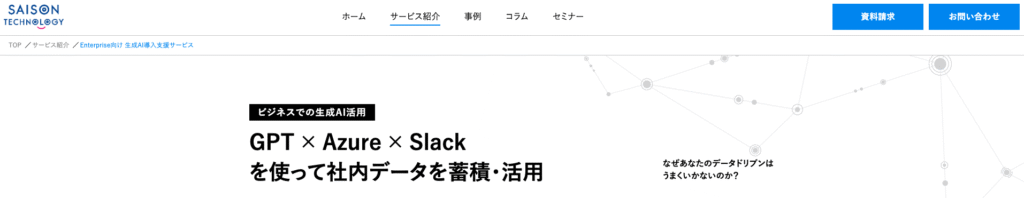
株式会社セゾンテクノロジーの「Enterprise向け 生成AI導入支援サービス」は、金融・流通などの高いセキュリティが求められる業界における豊富な開発経験を活かしたサポートが強みです。
サービスではGPT×Azure×Slackを用いた生成AI利用環境の構築と、社内利用ガイドライン(雛形)の提供を通じて、セキュリティに配慮したスモールスタートを支援してくれます。
特に、社内ルール整備に不安がある企業向けに、同社が整備した生成AI利用ガイドラインの雛形を参考情報として提供しており、社内規程づくりのたたき台として活用できます。
PoC支援や段階的なスモールスタートにも対応しており、「まずは一部業務から試したい」といったニーズにも柔軟です。
社内外のガバナンス要求に応じながら、安全かつ実践的に生成AIを導入したい企業に最適なパートナーです。
生成AI活用支援|株式会社ベルテクス・パートナーズ

株式会社ベルテクス・パートナーズが提供する生成AI活用支援は、「業務プロセスの変革」まで見据えた上流工程からのサポートが特長です。
単なる生成AIの導入支援にとどまらず、業務ヒアリングをもとに課題を抽出し、どこに生成AIを適用すべきか、どのような成果が期待できるかを明確にします。
また、導入効果の可視化やPoC支援、社内展開のための活用方針策定・教育まで含めた一気通貫の支援が可能です。
コンサルティングファームとしての実績を活かし、経営層・法務・情シスそれぞれの関心領域を押さえた丁寧な設計ができる点も安心材料です。
業務改革とAI導入を同時に進めたいと考える企業にとって、頼れるパートナーといえます。
生成AI導入支援サービス|TIS株式会社

TIS株式会社の生成AI導入支援サービスは、大企業向けシステム開発で培った信頼性と安定性を活かし、「堅実に導入を進めたい企業」から支持されています。
業種ごとの業務知見とAI技術を融合させ、個別業務に最適化された生成AI活用モデルを提案してくれます。
また、インフラ構築、セキュリティ設計、運用ポリシー策定までを網羅的にサポートしてもらうことも可能です。
特に、コンプライアンスやデータガバナンスへの対応力に優れており、社内ルールが厳しい業界でも安心して導入できます。
PoCによる効果検証も可能なため、社内承認プロセスが厳しい企業でも段階的にスムーズな展開が可能です。
実績重視・堅牢な体制で失敗リスクを減らしたい方におすすめです。
生成AI導入支援チーム|GMOコネクト株式会社
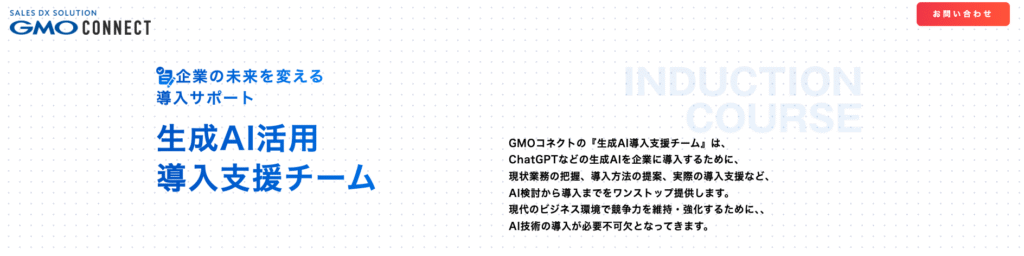
GMOコネクト株式会社の「生成AI導入支援チーム」は、企業内の生成AI利活用を「現場レベル」で実装することに強みを持つ伴走型サービスです。
社内の課題ヒアリングから活用領域の選定、導入方法の提案や実際の導入支援、社内教育までを一貫して支援し、現場部門が実務で生成AIを使いこなせる状態まで導きます。
特に、GMOインターネットグループとしてのセキュリティ運用経験を活かし、社内規程や情報管理基準への準拠も視野に入れた設計が可能です。
カスタムプロンプト作成や社内チャットボットの構築支援にも対応しており、小規模から始めて徐々に全社展開したい企業にも適しています。
「導入後の活用フェーズまでを含めてサポートしてほしい」と考える企業におすすめのサービスです。
生成AIセキュリティリスクマネジメント支援|株式会社GRCS
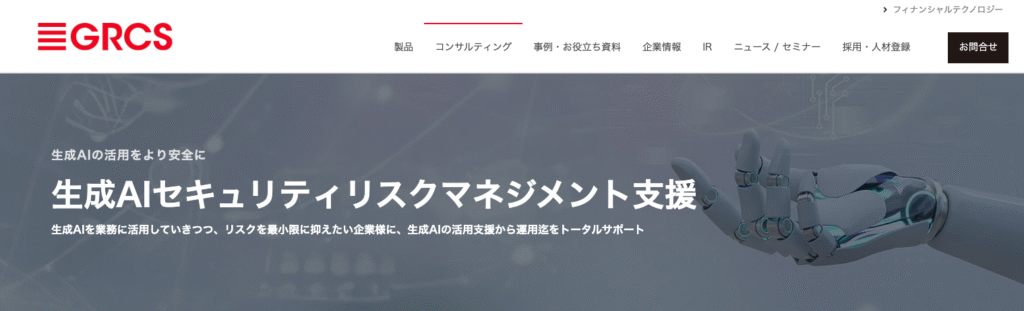
株式会社GRCSが提供する「生成AIセキュリティリスクマネジメント支援」は、情報漏洩や法的リスクに備えたセキュリティリスクのマネジメントを軸に、生成AIの利活用と守りの体制構築を両面から支援するサービスです。
サイバーセキュリティ・ガバナンスの専門企業として、生成AIの利用にともなう新たな脅威を洗い出し、リスク評価・対策ポリシーの整備・ログ管理方針の策定などを包括的に支援します。
社内の法務部門や情報セキュリティ委員会など、稟議・承認プロセスに関与する部署を納得させるための説明資料・ガイドライン作成も対応可能です。
「すでにPoCは実施済みだが、全社展開にあたり統制や安全性を確保したい」といったニーズにマッチしやすく、生成AI活用の信頼性を高めたい企業に適した選択肢です。
GMO即レスAI|GMOペパボ株式会社
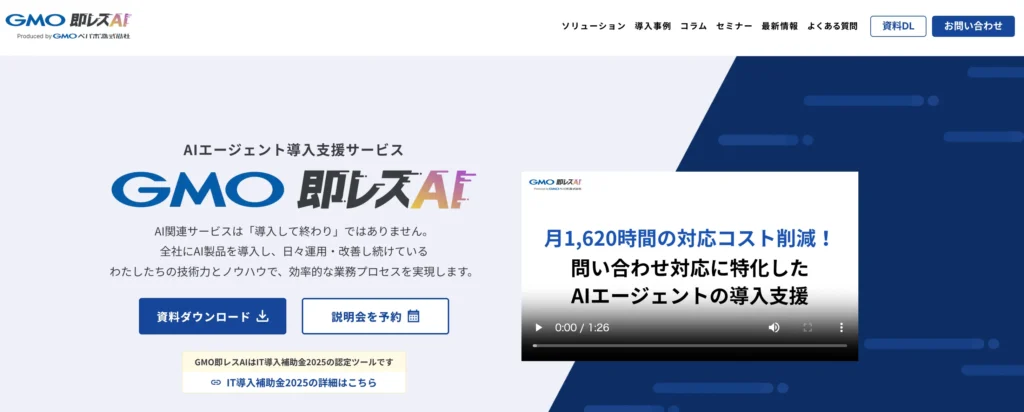
GMOペパボが提供する「GMO即レスAI」は、24時間365日稼働のAIチャットボットを導入から運用まで一括支援するサービスです。
特に、中小企業を中心に問い合わせ対応の自動化によって業務負荷を大きく削減し、顧客対応品質の向上にもつながっている点が評価されています。
シナリオ型チャットボットと生成AIのハイブリッド構成により、高精度な回答と柔軟な対応の両立を実現しており、初期設定や運用設計も丁寧にサポートしてくれます。
さらに、IT導入補助金対象サービスであるため、コスト面でも導入しやすい環境が整っていることも魅力のひとつです。
「問い合わせ対応を効率化したい」「初期導入から運用までを一気通貫で支援してほしい」といったニーズを持つ企業に適しています。
cloudpack 生成AI導入・活用支援サービス|アイレット株式会社
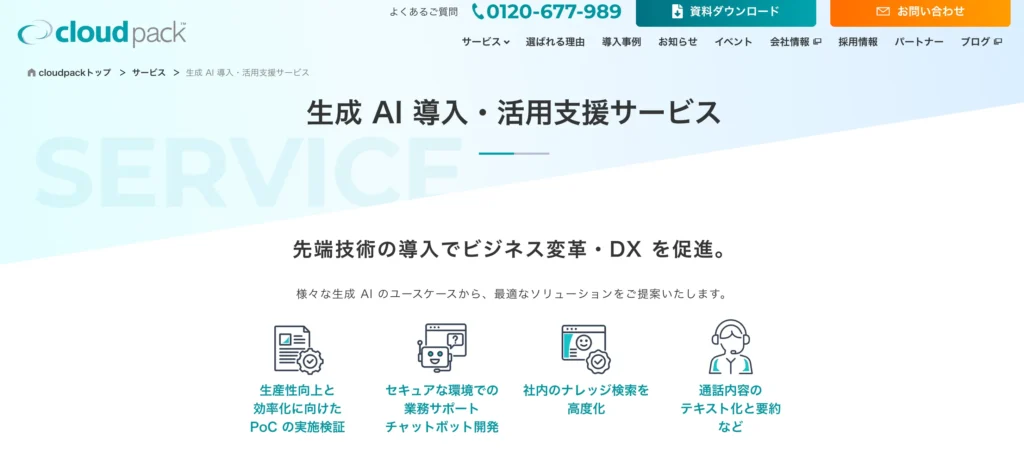
アイレットの「cloudpack 生成AI導入・活用支援サービス」は、AWSやGoogle Cloudを活用した生成AI導入を一貫してサポートしてくれるサービスです。
特に、Amazon BedrockやVertex AIといった先進的なクラウド技術を用いたPoC設計や業務実装に強みを持ち、実際にサポート業務の自動化によって1か月あたり約9人日分の工数削減を実現した事例もあります。
また、アイレットは長年にわたるクラウドインテグレーションの実績を持ち、AWSプレミアティアパートナーとしての信頼性と技術支援体制も充実しています。
「自社業務にフィットするAIの使い方を模索したい」「クラウドネイティブなAI導入を検討している」という企業におすすめです。
生成AIコンサルティング|NOVEL株式会社

NOVEL株式会社は、生成AIの実用導入に特化したコンサルティングと開発支援を提供しています。
課題整理から始め、ROIが見込めるユースケースの抽出、企画設計、PoC(概念実証)、本開発、さらには運用まで一貫して伴走する点が大きな強みです。
70万回以上利用された自社AIプロダクトの運営経験に基づく実践的知見と、書籍出版によるプロンプト設計ノウハウも持ち合わせており、深い技術と戦略の両面で信頼性があります。
「短期間で試せる形でAI導入を始めたい」「AIの内製化まで見据えた支援が欲しい」企業におすすめです。
生成AI導入支援サービス|株式会社キカガク

株式会社キカガクは、生成AIを業務に活かすための包括的な導入支援を行う企業です。
研修で培ったノウハウを活かした短期集中型プログラム「生成AIブートキャンプ」や、教育と開発を組み合わせた支援で、現場に定着する成果づくりを支援してくれます。
特に、企画立案から実装まで一気通貫で学べる体験重視のプログラムを強みとし、企業内でAI活用を牽引する人材を育成します。
スモールスタートと成功体験の積み重ねによって、全社展開につながる土台づくりをしたい企業におすすめです。
Graffer AI Solution 伴走支援|株式会社グラファー

グラファーの「Graffer AI Solution」は、生成AIを業務に安全に定着させるために、伴走支援・研修・プロダクト提供を一体化した包括的支援が特徴です。
企業の課題分析から導入検証、定着化、人材育成に至るまでの全段階で支援し、現場の混乱を避けつつ成果創出を目指せる体制を提供しています。
さらに、自社開発の「Graffer AI Studio」は、多様な業務テンプレートや強固なセキュリティ基盤を備え、どの部署でも活用しやすい設計です。
行政機関をはじめとした導入実績も多数あり、セキュリティ重視かつ業務に定着する支援を求める企業に特におすすめのサービスです。
生成AI活用支援|株式会社メンバーズ

メンバーズが提供する「生成AI活用支援」では、生成AIの導入から運用・定着までを伴走型で支援します。
生成AIリテラシー向上のための研修、業務の現場に即した課題抽出とMVP構築、SNS/広告/Web運営の自動化支援、さらにはAzure OpenAIベースのセキュアな自社利用環境構築まで、幅広い支援が特徴です。
実際に、データ集計業務の工数を月120時間から24時間に削減(約8割減)など、効果を実感できる導入成果も報告されています。
DX推進の現場で生成AIを継続的に活用したい企業におすすめといえます。
生成AIコンサルティング|ナイル株式会社

ナイル株式会社の「生成AIコンサルティング」は、生成AIによる業務改善を検討する企業に対して、業務可視化からプロトタイプ開発、PoC(概念実証)構築、効果シミュレーションまで一気通貫で支援するサービスです。
特に、「どの業務に適用すれば利益や効率向上につながるか」を定量的に評価しながら提案できる点が、導入失敗を抑えたい企業にとって安心できる選択肢です。
実際、玩具販売業界企業への導入を通じて、業務設計とコスト削減の成果を可視化し、社内理解を得る導入が実現しています。
生成AIの目的化を避け、自社の業務改善に直結するソリューションを求める企業に向いています。
AI導入支援サービス|株式会社FRONTEO
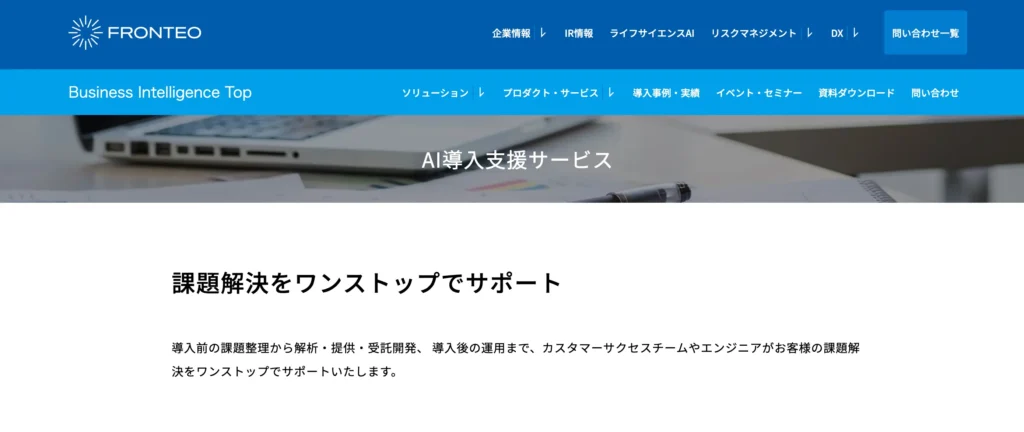
株式会社FRONTEOは自社開発のAIエンジン「KIBIT」による高度分析力と、AI導入から運用までをシームレスに支援する体制を強みとしています。
導入前の課題整理・精度検証・システム要件定義から、プロダクト導入、その後の運用・保守までをワンストップで支援する構成で、クラウド・オンプレミス・買い切り型の選択にも対応可能です。
金融やリーガル、製薬など専門業務に精通した高度な解析力が評価されており、セキュリティや専門性が重視される業界でのAI導入に適した選択肢です。
生成AI導入支援サービスとは?メリットを理解しよう
生成AI導入支援サービスとは、企業が生成AIを業務で安全かつ効果的に活用するための環境を整備し、導入から運用までを支援するサービスです。
サポート内容は活用目的の整理やPoC(概念実証)の設計、システム構築、データガバナンス対応、社内教育まで多岐にわたります。
導入を検討する企業の多くは、以下のような課題を抱えています。
- 社内にAIの専門人材がいない
- セキュリティや法的リスクへの対応に不安がある
- 稟議を通すための資料や根拠が不足している
- 自社に適したユースケースや導入手順がわからない
こうした課題に対し、導入支援サービスを活用すれば、手探りで進めるよりも短期間で成果につながりやすく、社内の説得やリスク対策もスムーズに行えます。
ここでは、導入支援サービスの利用によって得られるメリットをわかりやすく解説していきます。
業務効率化と無駄なコスト削減を実現できる
生成AIは単純作業の自動化や情報検索の高速化によって、日常業務の効率を大きく改善できます。
特に導入支援サービスを利用することで、現場の課題に即したAI活用の導線を設計できるため、無駄なツール導入や試行錯誤のコストを抑えることが可能です。
例えば、問い合わせ対応や文書作成、議事録の自動生成など、従来人手で行っていた業務の一部を置き換えることで、人件費や教育コストの削減にもつながります。
結果として、限られたリソースで高い生産性を維持したい企業にとって、生成AI導入は費用対効果の高い投資と言えるでしょう。
AIに詳しい担当者がいなくても実務で使える環境構築ができる
生成AIの導入は高度な専門知識が必要と思われがちですが、支援サービスを活用すれば専門人材がいなくても導入可能です。
多くの生成AI導入支援サービスは業務部門が直感的に使えるUI設計や、操作マニュアル・運用フローの整備、社内教育までサポートに対応しています。
また、初期構築時に業務要件をヒアリングし、AIの回答品質やリスクをコントロールする仕組みも組み込んでくれます。
そのため、「詳しい人材がいないから導入できない」と悩む企業も、スモールスタートで安心してAIの活用を始められるということです。
専門的なノウハウを短期間で獲得できる
生成AIの業務活用には、プロンプト設計やAIの限界を理解した上でのシナリオ設計が不可欠です。
導入支援サービスを利用すれば、蓄積された活用ノウハウや他社事例をもとに、自社の業務に適した活用方法を短期間で習得できます。
また、支援内容にはPoC支援や伴走型のワークショップが含まれることもあり、試行錯誤しながらAIの活用スキルを内製化していけます。
結果として、独自に学習するよりもスピーディかつ確実に、生成AIを使いこなす体制を構築できるということです。
ガバナンス強化と社内稟議をスムーズにする根拠資料を提供してくれる
生成AI導入には、情報漏洩や不適切利用のリスクを踏まえた社内ガバナンス体制の構築が求められます。
支援サービスはセキュリティ方針や利用規程の整備、稟議資料のテンプレート提供までを含めて対応してくれることが多く、法務や情報システム部門との調整もスムーズに進められます。
さらに、リスク評価の観点からベンダーや技術の選定根拠を明示するサポートもあり、監査や説明責任にも耐えうる体制構築が可能です。
こうしたサポートは、導入を進める現場担当者が社内理解を得る上で、非常に心強いです。
生成AI導入支援サービスを利用するリスクと注意点
生成AI導入支援サービスは非常に便利ですが、導入前に確認すべきリスクや注意点も存在します。
例えば、生成AI導入支援サービスを利用するにあたって、以下のような落とし穴もあります。
- 社外への情報漏洩リスク
- 特定ベンダーへの依存(ベンダーロックイン)
- 社内での活用ルールの未整備
- 利用目的のあいまいさによる失敗
こうした点を事前に理解しておくことで、適切な対策や社内調整が可能になり、トラブルの回避や投資対効果の最大化につながります。
ここでは、導入支援サービスを選ぶ上で見落とされがちなポイントやリスクを具体的に解説し、後悔しない導入のための判断材料を提供します。
情報が漏洩する可能性がある
生成AIを業務に導入する際は、社内データや機密情報が外部に漏れるリスクが現実的な懸念の一つです。
特に、外部のAIモデルとAPI連携する場合は、入力した情報が意図せず学習データに利用される可能性もあるため、対策が求められます。
このリスクに対応するためには、プライベートなLLM(大規模言語モデル)の構築や、データの匿名化・アクセス制御の徹底が有効です。
また、生成AI導入支援サービスを利用すれば、ガイドライン整備やログ監査の仕組みを含めたガバナンス構築も一括でサポートしてもらえます。
情報漏洩を防ぐには、技術的な制御だけでなく、社内ポリシーの明文化と運用設計がセットで求められることを理解しておく必要があります。
ベンダーロックインするとコストが増える
生成AIを導入する際に特定のベンダーに依存しすぎると、将来的な仕様変更や価格改定に柔軟に対応できなくなる恐れがあります。
例えば、使用しているAI基盤が一社独自のインフラやAPIに強く結びついている場合、切り替えコストや移行障壁が高くなりがちです。
このようなベンダーロックインを回避するには、OSS(オープンソースソフトウェア)の活用や、複数クラウドに対応した構成設計が効果的です。
導入支援サービスの中には、中立的な技術支援に特化し、将来の柔軟な構成変更を見越した提案をしてくれる事業者も存在します。
長期的な運用を見据えるなら、初期費用や利便性だけでなく、ベンダー依存度にも目を向けることが重要です。
生成AI導入支援サービスの失敗しない選び方
生成AI導入支援サービスを検討する上で、「どの会社に依頼すべきか」「自社に本当に合っているのか」といった悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。
選定を誤ると、セキュリティ対応の不備や導入後の運用トラブル、想定以上のコスト発生など、リスクが大きくなります。
そこで、以下のような観点から信頼できるサービスを見極めるポイントを紹介します。
- セキュリティ対策と情報管理の透明性
- 自社業種への理解と導入実績
- サポート体制・導入スピードの柔軟性
こうした要素を理解しておくことで、稟議を通しやすく、導入後も安定して運用できるサービスを選びやすくなります。
セキュリティ対応を確認して情報漏洩リスクをチェック
生成AI導入時に最も注意すべきリスクの一つが「情報漏洩」です。
特に、社内の業務データや個人情報をAIに入力する場合は、取り扱いが不適切だと重大なセキュリティ事故につながります。
導入支援サービスを選ぶ際は、データの保存・学習設定・アクセス制御の仕組みが整っているか、オンプレミスやクローズド環境への対応が可能かなど、具体的な対策を確認することが重要です。
また、社内向けの利用ガイドラインや監査ログ機能の整備もサービスに含まれていると、法務や情報セキュリティ部門の承認も得やすくなります。
業種別に生成AI導入支援の実績を確認する
生成AIの活用は業界や職種によって大きく異なるため、業種に応じた支援実績があるかどうかは重要な判断材料です。
例えば、製造業ではマニュアルの自動生成、金融業ではFAQ対応、医療ではカルテ要約といった活用が考えられます。
このような業務特性に応じたユースケースを理解し、業界の規制やデータの扱い方にも精通しているベンダーであれば、導入後のトラブルも起こりにくくなります。
サービス選定時には、過去の導入事例やクライアント一覧、活用成果のレポートなどを確認することがおすすめです。
サポート体制や導入スピード
生成AIの導入をスムーズに進めるためには、手厚いサポート体制と現実的な導入スケジュールの把握が欠かせません。
特に、初期段階ではPoC(概念実証)や社内調整が必要になるため、技術支援だけでなく、稟議用資料や教育コンテンツの提供があると社内展開が加速します。
また、緊急対応や運用フェーズでの改善提案など、導入後の伴走支援があるかも確認しましょう。
導入までに数か月かかるケースもあるため、自社のスケジュール感とサービス側の支援体制が合っているか事前にすり合わせておくことが重要です。
生成AI導入支援サービスの支援内容と導入フロー
生成AIを導入するには、単にシステムを整えるだけでなく、活用目的の明確化・セキュリティ対策・社内運用設計など多面的な検討が欠かせません。
そのため、支援サービスでは一般的に以下の3ステップに分けてサポートが行われます。
- コンサルティングフェーズ: 活用戦略の立案やPoC設計
- 環境構築フェーズ: インフラ・セキュリティ設計とシステム開発
- 運用・改善フェーズ: 効果測定・継続支援・社内定着化
これらの工程を通じて、自社に合った形での生成AI導入と運用を実現できる点が大きな魅力です。
ここでは、それぞれのフェーズで何が行われるのか、支援内容の具体例を交えてわかりやすく解説していきます。
コンサルティングフェーズ|課題整理と活用戦略策定
生成AI導入は、単にツールを導入するだけでは業務改善につながりません。
生成AI導入支援サービスは、まず現場の課題や業務フローを整理し、どの領域に生成AIを活用すべきかを可視化するコンサルティングフェーズを設けています。
この段階では、PoC(概念実証)の設計や社内ヒアリングを通じて、実現可能性・導入効果・リスクを事前に評価します。
目的と手段を明確にすることで、「導入したのに活用されない」といった失敗を防ぎましょう。
環境構築フェーズ|インフラ・セキュリティ設計
戦略が固まった後は、生成AIを安全かつ安定的に動かすための基盤構築が必要です。
支援サービスでは、クラウド/オンプレミスの選定、AIモデルの接続設計、社内データとの連携整備などを技術的に支援してくれます。
特に、重要なのは、アクセス権限管理・データの匿名化・ログ管理といったセキュリティ対策の設計です。
このフェーズで堅牢なインフラを構築できるかが、社内稟議の通過や運用後のリスク回避に直結します。
運用・改善フェーズ|効果測定と継続サポート
生成AIは導入して終わりではなく、実運用の中での改善と最適化が成果につながります。
生成AI導入支援サービスでは、定期的なログ分析や活用状況の可視化、ユーザー部門へのフィードバックなどを通じて、定着と効果最大化を支援します。
また、プロンプト設計の見直しや社内教育のアップデートにも対応している事業者であれば、生成AIを継続的に活かし続けられます。
こうした伴走型支援があることで、社内全体へのスムーズな展開やナレッジの蓄積も実現しやすくなります。

