トラブルを防ぎ、チーム全体の対応品質を安定させるために注目されているのがメール共有システムです。
メール共有システムは全体の管理を効率化できるだけでなく、外注先に業務委託する際でもセキュリティを保ちながらスムーズな運用ができるようになります。
本記事では、自社の課題を解決できるおすすめのメール共有システムを見つけて、顧客対応のスピードと信頼性を高める第一歩につなげましょう。
目次
メール共有システムとは?
メール共有システムとは、複数の担当者で同じメールアドレスを使い、問い合わせ対応や顧客対応をチーム全体で管理・共有できる仕組みです。
例えば、「誰がどのメールに対応したかわからない」「返信が遅れた」「外注先との引き継ぎがうまくいかない」といった課題を抱える企業で活用されています。
日々多くの問い合わせが届くサポート窓口や、複数拠点で顧客対応を行う企業では、1通のメールをチーム全員で見られることが大きな強みです。
メール共有システムはメール対応業務をより組織的に運用し、担当者が安心して業務を分担できる環境をつくるための基盤といえます。
OutlookやGmailとの役割の違い
OutlookやGmailは、メールの送受信を行う「メールアカウント管理の基盤」として広く利用されています。
企業ドメインのアドレスを発行したり、個人ごとに受信トレイを持ったりするなど、ビジネスに欠かせないインフラ的な役割を担います。
一方で、これらのサービス単体では、複数人で同じアドレスを共有しながら顧客対応を行う仕組みが不足しています。
担当者ごとの対応状況が見えにくく、引き継ぎや二重返信が発生しやすいのが課題です。
ここで活用されるのが、OutlookやGmailと同期し、受信メールをチーム全体で共有・可視化できる「メール共有システム」です。
対応ステータスやコメント機能を追加できるため、外注先や委託メンバーを含めた安全で効率的な対応体制を構築できます。
オンプレとクラウドはどちらが良い?
メール共有システムは「クラウド型」を選ぶ企業が圧倒的に多いです。
クラウド型はOutlookやGmailと連携でき、外注先やリモートワーカーも含めた安全な運用が可能です。
サーバーを自社で保有しないため、初期費用や保守コストも抑えられます。
一方、オンプレミス型は自社サーバー内で運用できるため、機密性の高い情報を扱う企業に向いていますが、導入やメンテナンスに数百万円単位の費用が発生することもあります。
また、「自作」する場合は開発・保守・セキュリティ対応をすべて自社で担う必要があり、数千万円規模の開発費がかかるケースも珍しくありません。
機能の拡張性や運用負担を考慮すると、多くの企業にとってはクラウド型の導入が現実的な選択肢です。
費用相場はクラウド型で月額600円からが目安
メール共有システムの費用は、「クラウド型」と「オンプレミス型」で大きく異なります。
クラウド型は一般的に初期費用0〜10万円前後、月額は1ユーザーあたり600〜13,800円が目安です。
例えば、メールワイズは600円〜、Zoho Deskは800円〜、Freshdeskは2,700円〜、Zendeskは8,000円前後といった価格帯です。
一方、オンプレミス型は自社サーバーで運用するため、初期費用が数百万円〜、月額も10万円以上になるケースがあります。
例えば、WEBCAS mailcenterは初期50万円〜、月額10万円〜が相場です。
クラウド型は初期負担が少なく、OutlookやGmailとの連携も容易なため、コストパフォーマンスと運用のしやすさの両面で多くの企業に選ばれています。
メール共有システムに搭載されている主な機能
メール共有システムには、チームでの対応を効率化し、属人化やミスを防ぐための多彩な機能が搭載されています。
以下では、代表的な機能とその役割を一覧で紹介します。
| ステータス機能 | 対応状況(未対応・対応中・完了など)を可視化して進捗を一元管理できる |
|---|---|
| 対応履歴 | 過去のやり取りを時系列で確認し、重複対応や属人化を防げる |
| コメント機能 | 社内向けのメモを残せるため、引き継ぎや外注連携がスムーズになる |
| 二重送信防止機能 | 他の担当者が返信中であることを自動通知し、誤送信を防止する |
| 返信文テンプレート | 定型文を登録しておくことで、スピーディーかつ統一感のある対応ができる |
| 集計レポート | 対応件数・時間・担当者別のデータを可視化し、改善に役立てられる |
| 自動振り分け機能 | 差出人や件名に応じてメールを自動分類し、対応漏れを防ぐ |
| 顧客情報の管理機能 | 顧客ごとの履歴や属性をまとめて管理し、対応品質を高められる |
ここでは、メール共有システムの主な機能から、以下の機能について詳しくご紹介していきます。
ステータス機能で対応者の処理状況を一元管理できる
ステータス機能とは、各メールが現在どの対応段階にあるのかをチーム全体で可視化できる仕組みです。
例えば、「未対応」「対応中」「完了」「保留」などの状態をひと目で確認できるため、複数人でのメール対応でも状況把握が容易になります。
従来のOutlookやGmailでは、対応の進捗をメンバー間で共有する手段が限られており、「誰が返信したのか分からない」「対応が重複した」といったミスが起こりがちでした。
メール共有システムのステータス機能を使えば、担当者や進行状況をリアルタイムで確認でき、業務委託先を含めた全員が同じ情報を基に動けるようになります。
結果として、対応漏れや認識違いを防ぎ、顧客対応のスピードと品質を同時に高めることができます。
メールの対応履歴がわかるのでチームで共有しやすい
メール共有システムでは、過去の対応履歴を時系列で確認できる機能が搭載されています。
そのため、「誰が・いつ・どのような」返信を行ったのかが可視化され、引き継ぎ時の確認作業や重複対応の防止に役立ちます。
従来のメール運用は担当者が個別の受信トレイで対応していたため、「前回どんな回答をしたのか」「顧客とのやり取りがどこまで進んでいるのか」が分かりにくく、属人化の要因になっていました。
対応履歴を共有できることで、新しい担当者や外注先も状況をすぐに把握でき、チーム全体で同じ顧客体験を提供できるようになります。
特に、サポート業務や営業サポートの現場では、過去対応の記録が品質維持の土台となり、顧客満足度向上にも直結します。
コメント機能があると細かい情報の引き継ぎも簡単になる
コメント機能はメール本文とは別に、チーム内でメモや補足情報を共有できる仕組みのことです。
担当者が対応の背景や顧客の要望、注意点などをコメントとして残すことで、次の対応者が状況をすぐに理解できます。
従来のメールでは口頭や別ツールで補足を伝える必要があり、情報の抜け漏れや伝達ミスが発生しがちでした。
コメント機能を活用すれば、1つのメール画面上で「やり取り内容」と「社内メモ」を分けて管理でき、外注先や新任担当者への引き継ぎもスムーズに行えます。
特に、顧客対応を複数人で行うチームでは、コメントを残す習慣がトラブル防止や対応品質の向上につながります。チーム全体が同じ情報を共有できることで、顧客ごとの対応方針を統一しやすくなります。
二重送信防止機能で安心感を持って顧客対応を任せられる
二重送信防止機能とは、同じメールに対して複数の担当者が同時に返信するミスを防ぐ仕組みです。
複数人で同一の受信ボックスを共有する環境では、対応状況が分からず同時に返信してしまうケースが起こりやすく、顧客からの信頼を損なう原因にもなります。
この二重送信防止機能を備えたメール共有システムは、返信中のメールが自動でロックされたり、「他の担当者が返信中」と通知されたりするため、誰がどの対応を行っているかを即座に把握できます。
特に、外注や委託メンバーを含むチーム運用では、リアルタイムで状況を共有できることが安心感につながります。
担当者同士が衝突せずに業務を進められることで、対応品質のばらつきが減り、企業全体で一貫した顧客対応を実現できます。
メール共有システムを導入する3つのメリット
メール共有システムを導入する最大の目的は、チーム全体での対応効率を高めながら、ミスや属人化を防ぐことです。
複数人で同じ受信ボックスを共有する体制では、対応状況が見えづらく、重複対応や返信漏れなどのトラブルが起こりやすくなります。
こうしたメール対応業務の課題を解消できるサービスが、メール共有システムです。
ここでは、メール共有システムを導入することで得られる以下のメリットを詳しく解説します。
メール対応業務に複数人アサインしても管理しやすい
メール共有システムを導入すると、複数の担当者が同じ受信トレイを使っていても、対応状況をリアルタイムで把握できるため、効率よく業務を進めながらミスを防げます。
従来のように個々のメールボックスで対応していると、誰が返信したのか分からず、二重対応や対応漏れが起こりがちでした。
ステータス機能やコメント機能を活用すれば、「誰がどの案件を担当しているのか」「今どの段階なのか」が明確になります。
これにより、外注メンバーを含めてもスムーズに引き継ぎができ、対応スピードと正確性が大幅に向上します。
結果として、少人数でも無理なくチーム対応ができ、顧客対応の品質を保ちながら業務全体の生産性を高められる点が大きなメリットです。
差出人別に自動振り分け機能で対応漏れを防げる
自動振り分け機能とは、差出人・件名・キーワードなどの条件に応じて、受信したメールを自動で分類・振り分ける仕組みです。
担当者や問い合わせ内容ごとにフォルダを分けられるため、未対応メールを見落とすリスクを大幅に減らせます。
従来のメール運用では、膨大な受信メールの中から手動で仕分けを行う必要があり、確認漏れや対応遅れが発生しやすい状況でした。
自動振り分け機能を使えば、たとえば「請求関連」「契約更新」「サポート」などのカテゴリに即時で仕分けされ、各担当者が優先度の高いメールに集中できるようになります。
また、対応済み・未対応を自動的に整理できるため、外注先や委託チームでも情報の行き違いを防止できます。結果として、対応スピードを維持しながらミスのない運用体制を構築できる点が大きな強みです。
各種履歴が残るので業務の属人化を防ぎやすい
メール共有システムでは、送受信履歴・対応履歴・コメント履歴などが自動的に蓄積されるため、担当者が変わっても過去の経緯をすぐに把握できます。
従来のメール運用では、特定の担当者のメールボックス内に情報が閉じてしまい、引き継ぎが難しくなることが多くありました。
履歴が共有化されることで、「前回のやり取り内容」や「過去の対応経緯」をチーム全員が確認でき、誰が担当しても同じ品質で対応を再現できる環境が整います。
特に外注や業務委託メンバーを含む体制では、履歴の一元管理が情報の抜け漏れ防止や教育コストの削減にも直結します。
結果として、担当者個人に依存しない仕組みが確立され、属人化のリスクを最小限に抑えながら継続的に高品質な顧客対応を実現できます。
メール共有システムの選び方
メール共有システムを選ぶ際は、まず操作のしやすさや導入後のサポート体制が整っているかを前提に考えることが大切です。
その上で、自社の運用環境や目的に合わせて、以下の4つの視点から比較検討すると失敗が少なくなります。
これらを総合的に確認することで、安全性と生産性を両立した運用体制を構築できます。
社内共有ツールやCRMツールなど必要なツールに連携できるか
メール共有システムを選ぶ際には、既存の社内SNSやCRM(顧客管理システム)との連携性を確認することが重要です。
メール対応は単体業務ではなく、問い合わせ管理や顧客データの更新、チーム内での情報共有など、他システムと密接に関わっています。
例えば、SlackやTeamsなどの社内コミュニケーションツールと連携できれば、返信状況を即座に共有でき、確認や承認の手間を減らせます。
また、SalesforceやHubSpotなどのCRMツールと連携すれば、メール対応内容を自動で顧客情報に反映でき、履歴管理が効率化します。
こうした外部ツールと連携できるかは、メール共有システムを選ぶ際に事前に確認しておきましょう。
メール共有システムから顧客管理を効率化したい場合は、ぜひビジトラが公表する「【2026年最新】CRMツールおすすめ比較15選!顧客管理の機能や選び方まで一覧で紹介」を参考にしてください。
誤送信防止機能やステータス管理機能で業務委託がしやすくなる
外注先や業務委託スタッフを含めてメール対応を行う企業は、誤送信防止機能やステータス管理機能が搭載されているかを必ず確認しておきましょう。
誤送信防止機能では、送信前のダブルチェックや上長承認を設定できるため、宛先や添付ファイルの誤りを未然に防げます。
社外メンバーが対応する場合でも、確認フローを通じてセキュリティを担保しながら対応品質を統一できます。
また、ステータス管理機能があるメール共有システムを活用すれば、各担当者がどの案件に対応しているか、どの程度稼働しているかを可視化することも可能です。
これにより、進捗管理と人員の稼働状況を同時に把握でき、外注チームの生産性を最大化できます。
担当者のアクセス制御ができる権限機能も確認しておこう
メール共有システムを選ぶ際は、担当者ごとにアクセス権限を設定できる機能が備わっているかを必ず確認しておきましょう。
複数の担当者や外注スタッフが同じアカウントを利用する場合、閲覧・編集・送信の範囲を制御できるかどうかで、情報管理の安全性が大きく変わります。
権限機能があれば、管理者は以下のように担当者の権限を柔軟に設定でき、誤操作や不要な情報閲覧によるリスクを防止できます。
- 閲覧のみ
- 返信可
- 設定変更可など
特に、業務委託やアルバイトスタッフを含む体制では、社内情報を必要な範囲だけ共有できる点が重要です。
また、退職者や契約終了メンバーのアクセスを即時に停止できるのもメリットです。
セキュリティを確保しながら、安心して外部メンバーと協働できる環境をつくるための基盤として、権限管理機能は欠かせません。
さらに業務を効率化できるAI機能があるサービスもある
メール対応業務を徐々に自動化させていきたい場合は、AI機能が搭載されているサービスにも注目しましょう。
近年のメール共有システムでは、AIが対応を支援する機能を搭載したサービスが増えています。
例えば、Re:lationでは、AIチャットボットが問い合わせ内容を自動で解析し、一次対応やクレーム検知を行う機能を備えています。
Mail DealerではAIが本文を分析して返信文のドラフトを自動生成し、担当者は確認・修正するだけで返信が完了します。
yaritoriではAIエージェントが文面の提案やテンプレートの自動選択を行い、対応スピードと品質の両立を実現しています。
こうしたAI機能を活用することで、単なる業務効率化にとどまらず、対応品質の標準化や属人化の解消が可能です。
対応件数が多い企業ほど、AI機能の有無が生産性に大きく影響するでしょう。
おすすめのメール共有システム12選を比較
ここでは、機能性・導入実績・コストパフォーマンスの3点を軸に、代表的な12のメール共有システムを比較しました。
対応履歴の共有やAIによる返信支援など、各サービスの強みを理解することで、自社に最適なツールを選びやすくなります。
「チームで安心して顧客対応を任せられる環境」を整える第一歩として、導入効果の高いサービスを検討してみましょう。
メールワイズ

メールワイズは、サイボウズ株式会社が提供するクラウド型のメール共有システムです。
対応履歴・コメント・ステータス管理など、問い合わせ対応に必要な機能を網羅しています。
既に同社グループウェアを導入している企業は、認証や通知を共通化することで社内の情報共有をよりスムーズに行えます。
また、kintoneとは専用プラグインを通じて連携でき、顧客情報や対応履歴を一元管理することも可能です。
直感的でシンプルなUI設計により、初めてメール共有ツールを導入する企業でも運用を定着させやすい点が評価されています。
クラウド版スタンダードコースは1ユーザーあたり月額600円(5ユーザーから)と導入コストも抑えられており、特に中小企業や部署単位での利用に適しています。
楽楽自動応対

楽楽自動応対(旧:メールディーラー)は株式会社ラクスが提供する国内導入実績トップクラスのメール共有システムです。
以前は、メールディーラーという名称で運営されていましたが、楽楽自動応対にブランドが統一されました。
長年にわたりカスタマーサポート・EC事業者など多業種で利用されており、高い信頼性と豊富な機能性が評価されています。
特に、誤送信防止や返信漏れ防止の仕組みが強化されており、メール送信時の承認フローやアラート機能により、外注スタッフを含めた体制でも安全に運用できます。
また、テンプレート・自動振り分け・レポート分析などの機能を標準搭載し、高いセキュリティとチーム管理性を両立しています。
中〜大規模組織やカスタマーサポート部門など、問い合わせ対応が多い企業に最適な選択肢です。
運用サポート体制も充実しており、導入後も安定した利用が期待できます。
Re:lation(リレーション)

Re:lation(リレーション)は株式会社インゲージが提供する高機能なクラウド型メール共有システムです。
メール・LINE・Twitter・チャットなど、複数チャネルでの問い合わせを1つの画面に統合管理できる点が大きな特徴です。
AIチャットボットなどのAI機能を搭載しており、問い合わせ内容や蓄積されたナレッジをもとに返信案の自動生成やFAQサイトの自動作成、メールの自動返信などが行えます。
ステータス管理やラベル・アラート機能と組み合わせることで、クレームにつながりそうな問い合わせを素早く把握し、対応ミスや顧客離脱のリスクを減らすことができます。
また、ステータス管理やコメント機能など、チームでの共有・引き継ぎもスムーズです。
サポート業務を複数チャネルで運用している企業や、問い合わせ対応の質とスピードを両立したい中〜大規模企業に特に適しています。
セキュリティ対策も万全で、外注・在宅スタッフを含めた運用にも安心感があります。
WEBCAS mailcenter

WEBCAS mailcenterは株式会社WOW WORLDが提供する大企業・官公庁向けの高セキュリティなメール共有システムです。
オンプレミス・クラウドの両対応で、機密性の高い情報を扱う企業にも柔軟に対応できます。
大量のメール処理を自動化できる振り分け機能や、担当者別の権限設定・承認フローなど、ガバナンスを重視した設計が特徴です。
また、過去の対応履歴やレポートを分析できるため、チームの対応品質や稼働状況を定量的に把握できます。
サポート窓口・金融・公共機関など、情報管理の厳格さを求める組織に最適なシステムであり、導入後のサポート体制も充実しています。
Zendesk

Zendeskは世界中で導入されているグローバル標準のカスタマーサポートプラットフォームです。
メール共有機能に加え、チャット・SNS・電話など複数チャネルの問い合わせを統合管理でき、顧客対応を一元化できます。
ステータス管理や自動振り分け機能はもちろん、AIが問い合わせ内容を分析して優先度の高いチケットを自動で分類・提案するなど、サポート業務を効率化する機能が豊富です。
さらに、SalesforceやSlackなど主要な外部ツールとも容易に連携可能で、既存の業務フローに組み込みやすいのも魅力です。
グローバル対応・拡張性・AI活用を重視する企業に最適で、多拠点での顧客対応を安定的に運用したい中〜大規模組織に向いています。
Zoho Desk

Zoho Deskは、Zoho社が提供するコストパフォーマンスに優れたクラウド型ヘルプデスクツールです。
メール・SNS・チャットなどの問い合わせを一元管理でき、担当者ごとにステータスや進捗を明確に可視化できます。
AIアシスタント「Zia(ジア)」が問い合わせ内容を自動解析し、返信候補の提案やナレッジ記事の推薦を行う点が特徴です。
これにより、対応スピードを維持しながら属人化を防ぐことができます。また、Zoho CRMやSlackとの連携も容易で、顧客データを活用した一貫したサポートが可能です。
低コストで高機能なメール共有ツールを探している中小企業やスタートアップに特におすすめで、スモールスタートから段階的に機能拡張できます。
問いマネ
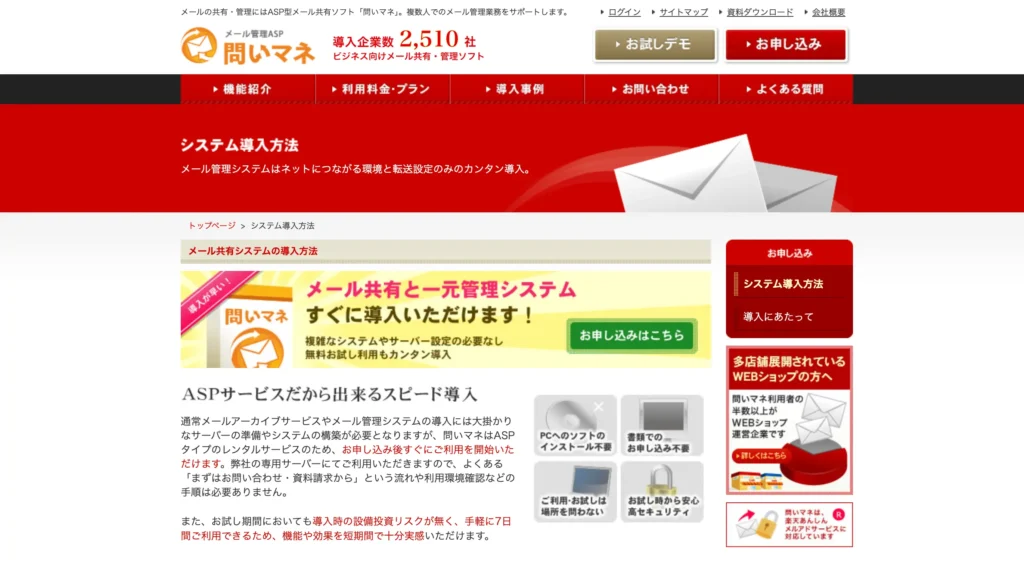
問いマネはクロスセル株式会社が提供する、チームでの問い合わせ対応を効率化できるメール共有システムです。
複数人で1つのメールアドレスを管理でき、担当者の割り当てや対応ステータスの共有、コメント機能など、チーム運用に必要な機能を標準搭載しています。
重複返信を防ぐアラート機能や、テンプレートを使った返信文の共有により、対応の抜け漏れや表現のばらつきを防止できます。
導入ハードルも低く、サーバー設定後すぐに運用を開始できる手軽さが特徴です。
料金は初期費用11,000円、月額3,124円(10ユーザー込)から利用可能で、30ユーザー向けの上位プランも用意されています。
低コストでシンプルな運用を重視する中小企業やスタートアップに最適なメール共有システムです。
mi-Mail

mi-Mail(エムアイメール)は未創システム株式会社が提供する、セキュリティと内部統制を重視したメール共有システムです。
クラウド型と専用サーバー型の両方に対応しており、企業のセキュリティポリシーや運用規模に応じた導入が可能です。
誤送信防止のための承認フロー機能や、アクセス権限の細分化、操作ログの記録など、安心して外部メンバーを含めたチーム運用ができる仕組みを備えています。
対応履歴やスレッド表示によるメール管理にも優れており、過去対応の検索・共有が容易です。
料金はスタンダードプランで、初期費用が30,000円で月額費用が15,000円から利用することができます。
大量メールを扱う企業やセキュリティ要件の厳しい組織にも対応しており、カスタマーサポートや官公庁などでの導入にも向いています。
Tayori

Tayori(タイヨリ)は株式会社PR TIMESが提供するクラウド型のお問い合わせ対応・顧客対応支援ツールです。
フォーム・メール・チャット・FAQ(ヘルプページ)を一元管理でき、スモールチームでも手軽に導入しやすいのが特徴です。
メール共有機能では、チーム全員で問い合わせ内容を確認し、対応ステータスを管理できます。
コメント機能を使えば、担当者同士で補足情報を共有できるため、社内外のやり取りをスムーズに行えます。
また、FAQページを自動生成できる「よくある質問」機能や、チャットウィジェットとの連携も可能で、顧客対応の一次回答を自動化できます。
コストを抑えつつ、問い合わせ対応の抜け漏れや属人化を防ぎたい中小企業・ベンチャー企業に最適なメール共有ツールです。
Freshdesk

Freshdesk(フレッシュデスク)はインド発のZoho同様にグローバルに展開する「Freshworks社」が提供するクラウド型のヘルプデスク・問い合わせ管理システムです。
メール、チャット、電話、SNSなど複数チャネルを統合し、顧客対応をチーム全体で可視化・共有できます。
自動チケット化やステータス管理、SLA(対応期限)設定など、サポート品質を維持するための機能が豊富に搭載されています。
また、AIアシスタント「Freddy AI」により、問い合わせ内容の分類や優先度判定、返信内容の提案などを自動で行えるのも特徴です。
SalesforceやSlack、Microsoft Teamsなど主要ツールとの連携にも対応しており、既存の業務フローに組み込みやすい点も魅力です。
中〜大規模のサポート組織や、グローバル対応を視野に入れた企業に適した高機能なメール共有システムといえます。
Grp Mail

Grp Mail(グループメール)は、キー・ポイント株式会社が提供しているメール共有・管理システムです。
1つのメールアドレスを複数人で共有し、対応状況を一元化して管理する設計です。
対応ステータス(未対応・対応中・返信待ち等)を表示でき、誰がどのメールを担当しているか把握しやすく、二重返信や対応漏れを抑制する機能を備えています。
また、ユーザ・管理者など複数段階の権限設定が可能で、操作履歴やログを追える設計になっています。
複数拠点を持つ組織やメール対応体制を構築したい企業にとって、有力な選択肢になり得るシステムと言えるでしょう。
チャネルトーク

チャネルトーク(Channel Talk)は、株式会社Channel Corporationが提供するWeb接客/コミュニケーションプラットフォームです。
チャット機能を中核に据えつつ、LINEやInstagramなどのチャネル連携やCRM機能も備えており、複数チャネルの顧客対応を統合的に管理できます。
チャネルトークにはAI エージェント「ALF」やシナリオ型チャットボット機能があり、よくある質問への自動応答を補助する仕組みが用意されています。
社内向けビジネスチャット機能も提供されており、顧客対応をしながら社内でリアルタイムに情報共有や引き継ぎを行うことが可能です。
CRM機能では顧客プロファイルや会話履歴を蓄積・参照でき、問い合わせの文脈を踏まえた対応がしやすくなります。
これにより対応の属人化を抑制する設計がなされている点が評価されます。
チャットを主軸としながらも、CRM/マーケティング用途への拡張や他チャネル統合も視野に入れた柔軟性を持つプラットフォームといえるでしょう。

